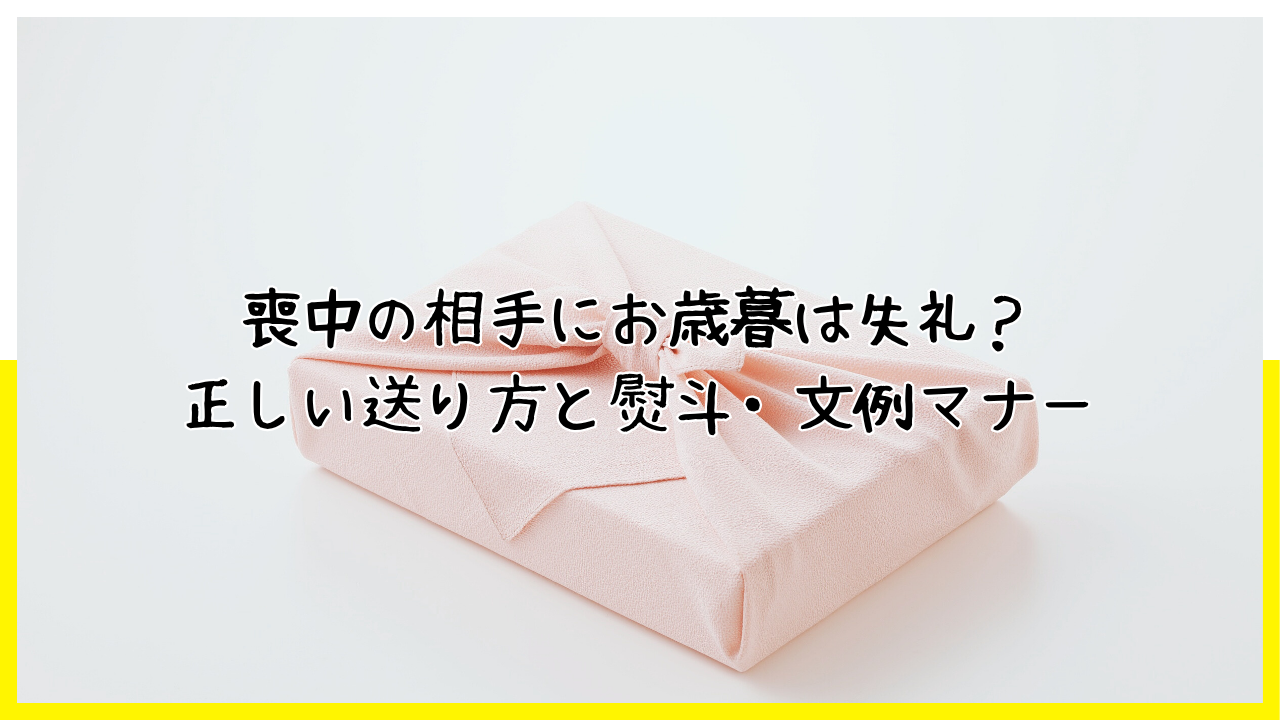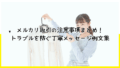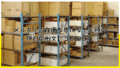「喪中の相手にお歳暮を送ってもいいの?」と迷った経験はありませんか。
お歳暮は「お祝い」ではなく、日頃お世話になった方への感謝の気持ちを伝える贈り物です。
そのため、喪中であっても失礼にはあたりませんが、贈る時期やのし紙、送り状の文面には注意が必要です。
この記事では、喪中や忌中の時期にお歳暮を贈るときのマナーを、誰でもわかるやさしい言葉で丁寧に解説します。
「贈るのを控えた方がいい?」「どんな品がふさわしい?」といった疑問も、文例付きでしっかりカバー。
正しいマナーを知って、相手に安心と温かさが伝わるお歳暮を贈りましょう。
喪中の相手にお歳暮を送るのは失礼?まずは考え方を整理しよう
喪中の時期にお歳暮を贈るのは失礼なのか――この疑問は、多くの人が一度は抱くものです。
実はお歳暮は「お祝い」ではなく、日頃お世話になった方へ「感謝」を伝えるための贈り物です。
そのため、基本的には喪中であっても贈って問題ありませんが、時期や気遣い方にいくつかのポイントがあります。
喪中と忌中の違いをやさしく解説
まず知っておきたいのが、「喪中」と「忌中」の違いです。
喪中とは、身近な人を亡くした後に一定期間、故人をしのび静かに過ごす期間のこと。
一方で忌中(きちゅう)は、その中でも特に慎み深く過ごす時期で、仏教では四十九日が過ぎるまで、神道では五十日祭までを指します。
つまり、忌中は喪中の一部であり、より慎重に行動する時期ということです。
| 区分 | 期間の目安 | 意味 |
|---|---|---|
| 忌中 | 約49〜50日 | 故人を悼み、外部とのやり取りを控える時期 |
| 喪中 | 約1年間 | 故人を偲びつつ、徐々に日常を取り戻す時期 |
お歳暮は「お祝い」ではなく「感謝」を伝える贈り物
お歳暮は、年末にお世話になった方へ感謝の気持ちを届ける日本独自の文化です。
そのため、結婚や出産などの「慶事」とは異なり、喪中であってもお歳暮を贈ること自体はマナー違反ではありません。
お歳暮=感謝の贈り物であることを理解しておくと、判断に迷う場面でも落ち着いて対応できます。
忌中の時期は避けたほうがよい理由
ただし、忌中の間は贈る時期として適切ではありません。
この期間は、遺族が故人を想い静かに過ごす大切な時期であり、贈り物を受け取る心の余裕がない場合もあります。
そのため、お歳暮を贈る場合は忌明け(四十九日・五十日祭)を過ぎてからが望ましいとされています。
忌中の時期を避けることで、相手への思いやりと礼儀の両方を保てます。
喪中の相手にお歳暮を贈るときの基本マナー
喪中の相手にお歳暮を贈るときは、相手の心情に寄り添った対応が大切です。
形式や金額よりも、「相手を思いやる気持ち」が最も重要なマナーになります。
ここでは、送るタイミングや宛名、宗教的な配慮など、贈る前に確認しておきたい基本ルールを整理します。
贈ってよいタイミングと避けるべき時期
お歳暮の一般的な時期は、12月上旬から20日頃までとされています。
ただし、相手が喪中の場合は、忌中を避けることが第一のポイントです。
忌明け後であれば、喪中の期間中でも感謝の気持ちとしてお歳暮を贈って問題ありません。
もし忌明けが年明けにずれ込みそうな場合は、「お歳暮」ではなく「寒中見舞い」として1月8日以降に贈るのが丁寧です。
| 贈るタイミング | 表書き | 備考 |
|---|---|---|
| 12月上旬〜20日頃 | 御歳暮 | 一般的な時期(忌中は避ける) |
| 1月8日〜2月初旬 | 寒中御見舞/寒中御伺 | 忌明けが年を越した場合 |
故人宛ではなくご遺族宛に送るのがマナー
故人宛にお歳暮を送るのは避けましょう。
お歳暮は「感謝の気持ちを伝える贈り物」ですので、すでに故人が亡くなっている場合は、ご遺族の方宛に送るのが適切です。
ただし、ご遺族がまだ悲しみに暮れている時期であれば、無理に贈る必要はありません。
長年お世話になった方の家族に対して、「お付き合いを大切にしたい」という気持ちを込めて贈る場合は、控えめな包装と落ち着いた文面を心がけましょう。
相手の宗教・信仰による違いにも配慮を
宗教によって、喪中の考え方には違いがあります。
たとえば、仏教や神道では「忌中を避ける」という考え方がありますが、キリスト教では忌中という概念がなく、贈答に特別な制限もありません。
相手がどのような宗教・信仰を持っているかを事前に知っておくと、より丁寧な対応ができます。
相手にとって心地よいタイミングで贈ることこそ、最も大切なマナーです。
喪中のお歳暮で気を付けたい「のし」と「包装紙」の選び方
喪中のお歳暮では、贈る時期だけでなく、見た目の印象にも注意が必要です。
特に「のし(掛け紙)」や「包装紙」は、相手への気遣いが最も伝わる部分です。
ここでは、喪中のお歳暮にふさわしいのしや包装紙のマナーを解説します。
紅白水引はNG、白無地奉書紙が最適
通常のお歳暮では、紅白の蝶結び水引付きののし紙を使います。
しかし、喪中の相手に贈る場合は、紅白の水引は避けるのが基本です。
紅白は「慶事(お祝い)」を連想させるため、喪中の贈り物には不向きとされています。
その代わりに使うのが、白無地の奉書紙や、白い短冊です。
表書きには「御歳暮」と記し、控えめで落ち着いた印象に仕上げましょう。
| 状況 | のし紙の種類 | 表書き |
|---|---|---|
| 喪中の相手へ贈る | 白無地奉書紙または短冊 | 御歳暮 |
| 忌明けが年明けにずれた場合 | 白無地奉書紙 | 寒中御見舞/寒中御伺 |
「内のし」で控えめに、落ち着いた印象を演出
のし紙をかける位置にもマナーがあります。
華やかな印象になりやすい「外のし」ではなく、「内のし」(品物にのしをかけてから包装紙で包む方法)を選ぶのがおすすめです。
内のしにすることで、見た目に落ち着きが出て、相手に配慮した印象を与えます。
お歳暮の趣旨が感謝であることを大切にし、あくまで控えめな贈り方を意識しましょう。
包装紙はグレー・白・薄紫など落ち着いたトーンを選ぶ
包装紙は、のしと同じく重要なマナーの一部です。
華やかな柄や赤・金などの鮮やかな色は避け、落ち着いた色合いを選びましょう。
おすすめは、グレー、白、薄紫などの控えめな色味です。
また、柄入りの場合も、無地に近いデザインや和紙調の質感が上品で好印象です。
| 避ける色・柄 | おすすめの色・柄 |
|---|---|
| 赤、金、ピンク、大柄の花模様 | 白、グレー、薄紫、無地や和紙調 |
「派手さよりも、誠実さ」を意識することで、心のこもった印象を自然に伝えられます。
喪中に贈るお歳暮の送り状・挨拶文マナー
喪中の相手にお歳暮を贈るときは、送り状や挨拶文の内容にも細やかな配慮が求められます。
特に言葉選びには注意が必要で、お祝い事を連想させる表現や、繰り返しを意味する言葉は避けましょう。
ここでは、避けるべき表現と、実際に使える文例を紹介します。
避けるべき言葉と使ってよい表現
送り状に「おめでとうございます」や「お慶び申し上げます」といったお祝いの言葉を入れるのは避けましょう。
また、「ますます」「重ね重ね」などの重ね言葉や、「死」「苦」「九」などの不吉とされる言葉も避けます。
代わりに、「ご健勝をお祈りいたします」「穏やかにお過ごしください」など、相手の安らぎを願う表現を使うのが良いでしょう。
| 避ける表現 | 推奨される表現 |
|---|---|
| おめでとうございます | お世話になっております |
| ますますご繁栄のことと | お変わりなくお過ごしでしょうか |
| 重ね重ねお礼申し上げます | 平素よりご厚情を賜り御礼申し上げます |
喪中の相手に贈る送り状の文例(テンプレ付き)
お歳暮に添える送り状は、感謝と気遣いを伝えることが目的です。
ここでは、どんな状況にも使いやすい基本文例を紹介します。
【文例】喪中の相手にお歳暮を贈る場合
拝啓
年の瀬を迎え、何かとお忙しい時期かと存じます。
平素は一方ならぬお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
心ばかりの品をお送りいたしましたので、ご笑納いただけましたら幸いに存じます。
寒さ厳しき折、どうぞお体にお気を付けてお過ごしください。
敬具
このように、形式はシンプルで構いません。
相手の気持ちを思いやる一文を添えることが最も大切です。
寒中見舞いに切り替える場合の挨拶文例
お歳暮の時期を逃した場合や、忌中と重なってしまった場合は、「寒中見舞い」として贈るのが適切です。
表書きを「寒中御見舞」または「寒中御伺」とし、文面も季節の挨拶に合わせます。
【文例】寒中見舞いとして贈る場合
拝啓
寒さ厳しい折、いかがお過ごしでしょうか。
旧年中は大変お世話になり、心より感謝申し上げます。
心ばかりの品をお送りいたしましたので、ご笑納いただければ幸いです。
本年も変わらぬお付き合いのほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
敬具
寒中見舞いは、お歳暮よりもさらに控えめな印象で、喪中の相手にも受け入れられやすい方法です。
自分が喪中のときのお歳暮マナー
喪中のときにお歳暮を贈るべきか迷う方も多いですが、自分が喪中であっても、感謝の気持ちを伝えるお歳暮は問題ありません。
ただし、時期や贈り方に配慮することで、相手に気を遣わせず、自然な形で心を届けることができます。
ここでは、自分が喪中の場合に知っておきたい基本マナーを整理します。
忌中期間は控え、忌明け後に贈る
自分が喪中の場合でも、お歳暮を贈ること自体は失礼にはなりません。
ただし、忌中の期間(四十九日・五十日祭が終わるまで)は贈るのを控えるのが一般的です。
忌明け後であれば、いつも通りの時期に贈って構いません。
忌明けが年をまたぐ場合は、1月8日以降に「寒中見舞い」として贈るのが丁寧です。
| 状況 | 対応方法 |
|---|---|
| 忌中(49日・50日祭前) | お歳暮を控える |
| 忌明け後(12月中旬以降) | 通常通り贈ってOK |
| 忌明けが年明け以降 | 寒中見舞いとして贈る |
のし紙・包装紙の選び方は相手が喪中のときと同じ
自分が喪中の場合も、使うのし紙や包装紙は相手が喪中の場合と同じマナーで構いません。
紅白の水引は避け、白無地の奉書紙か短冊を使いましょう。
また、のし紙を「内のし」にして控えめに包むと、落ち着いた印象になります。
包装紙も派手な色柄を避け、白やグレーなどの上品な色を選ぶのが基本です。
「今年は控える」も立派なマナーのひとつ
自分の心がまだ落ち着かない場合や、相手に気を遣わせたくないときは、お歳暮を無理に贈らないという選択も立派なマナーです。
お歳暮の目的は「感謝を伝えること」であり、形式を守ることではありません。
気持ちが整ったときに改めてお礼を伝えたり、寒中見舞いで感謝の気持ちを表すのも良い方法です。
形式よりも、相手に配慮する姿勢こそが最も大切なマナーだといえるでしょう。
喪中のお歳暮に選ぶべき品と避けるべき品
喪中のお歳暮では、どんな品を贈るかにも気配りが求められます。
派手すぎるものや慶事を連想させる品は避け、相手が受け取りやすい落ち着いた贈り物を選びましょう。
ここでは、避けたほうがよい品と、喪中でも安心して贈れるおすすめの品を紹介します。
避けたほうがよい「生もの」や「縁起物」
喪中に避けたいのは、昔から「お祝い」や「縁起」を象徴する品です。
特に、紅白の色合いが強い食品や、祝い事に使われる食材・柄物などは控えるのが無難です。
また、鰹節・昆布など、慶事の贈答に使われる品も避けましょう。
| 避けたほうがよい品 | 理由 |
|---|---|
| 紅白の食品セット | 慶事を連想させる色合いのため |
| 鰹節・昆布 | お祝いごとの縁起物とされているため |
| 華やかな花束やギフト | 祝い事を連想させるため |
おすすめの品(お菓子・お茶・日用品・カタログギフト)
喪中の方には、落ち着いた印象の品を選ぶのが好ましいです。
相手の生活に寄り添うような実用的な贈り物は、気持ちが伝わりやすく、負担にもなりません。
たとえば、日持ちするお菓子やお茶のセット、上品なタオルギフトなどが定番です。
また、カタログギフトなら、相手が好きな品を自由に選べるため、相手に負担をかけずに感謝を伝えることができます。
| おすすめの贈り物 | 特徴 |
|---|---|
| 焼き菓子や煎餅など日持ちするお菓子 | 控えめで上品な印象。保存しやすい |
| 緑茶・紅茶などの飲み物ギフト | 年末の挨拶品として落ち着いた定番 |
| タオル・石けんなどの日用品 | 消耗品として実用的で喜ばれやすい |
| カタログギフト | 相手が自由に選べる安心の形式 |
もらった相手の気持ちが和らぐ「心遣いの品選び」
お歳暮の品は「華やかさ」よりも「思いやり」で選ぶことが大切です。
派手なものを避け、落ち着いた色味や包装のものを選ぶだけでも、印象がぐっと柔らかくなります。
また、メッセージカードや送り状に、相手を気遣う一文を添えることで、より温かみが伝わります。
贈り物は「品」よりも「心」。それを意識することで、喪中でも安心して感謝を届けられるお歳暮になります。
まとめ:マナーを守って、感謝を丁寧に伝えるお歳暮を
喪中の相手にお歳暮を贈ることは、決して失礼ではありません。
お歳暮は「感謝の気持ち」を伝える日本の美しい習慣であり、相手を思いやる心があれば、喪中でも問題なく贈ることができます。
ただし、贈る時期や包装、言葉遣いに少しだけ配慮を加えることで、相手に安心と誠意が伝わります。
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 時期 | 忌中は避け、忌明け後に贈るのが理想 |
| のし紙 | 紅白ではなく白無地の奉書紙を使用 |
| 包装紙 | 落ち着いた色合い(白・グレー・薄紫など) |
| 送り状 | お祝い言葉を避け、穏やかな表現で感謝を伝える |
| 品選び | 派手すぎず、実用的で落ち着いた品を選ぶ |
もし忌中と時期が重なる場合は、無理に贈らず、寒中見舞いとして改めて気持ちを伝えましょう。
喪中という繊細な時期だからこそ、形式ではなく相手の心に寄り添う姿勢が何よりのマナーです。
思いやりと感謝の心を込めて贈るお歳暮は、相手にとっても温かい記憶として残るでしょう。