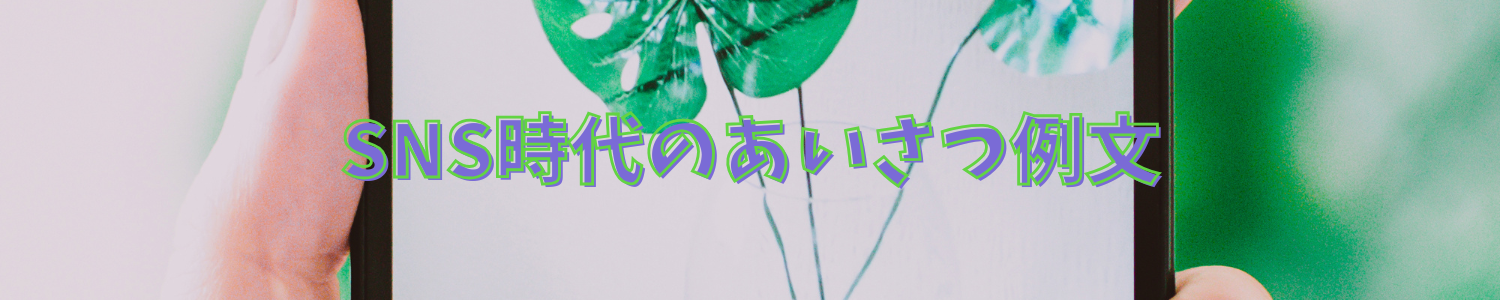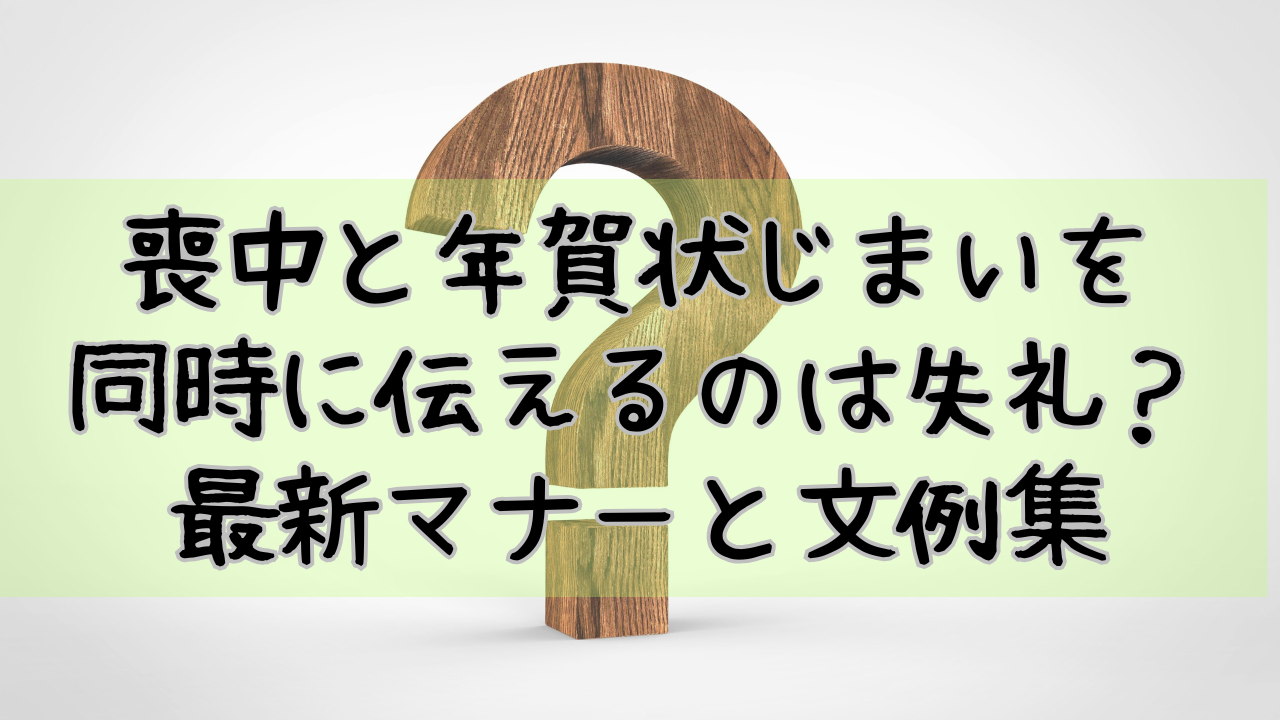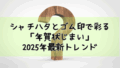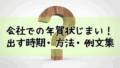「喪中」と「年賀状じまい」が重なったとき、同時に伝えてもよいのか迷う方は多いのではないでしょうか。
近年は年賀状じまいを選ぶ人が増えており、喪中はがきを出す機会を「最後の年賀状」として活用するケースも見られます。
しかし一方で、ご年配や目上の方にとっては「突然すぎる」と受け止められることもあるため、伝え方やタイミングには注意が必要です。
本記事では、喪中と年賀状じまいを同時に伝える場合の正しいマナーやタイミング、相手別に使える文例を多数紹介します。
あなた自身の立場や相手との関係性に合った伝え方がわかるように整理しましたので、安心して活用いただけます。
「失礼にならないかな…」と不安な方も、この記事を読めば迷わずに準備できるはずです。
喪中と年賀状じまいを同時に伝えるのは失礼か?
喪中はがきと年賀状じまいを同時に伝えることは可能ですが、相手によっては「唐突」と感じられることもあります。
ここでは、同時に伝えてよいケースと、避けたほうがよい場合の違いを整理します。
同時に伝えてよいケースと注意点
喪中はがきに「年賀状じまい」を添えること自体は、マナー違反ではありません。
とくに近年は、年賀状文化の縮小に伴い、喪中の機会を「年賀状じまい」の節目とする方も増えています。
喪中と年賀状じまいを同時に伝えることは失礼ではなく、むしろ自然な流れと受け止められる場合が多いのです。
ただし、文章全体のトーンを落ち着いたものにし、控えめに記すことが大切です。
| 伝え方 | ポイント |
|---|---|
| シンプルに伝える | 喪中を主とし、年賀状じまいは一文に留める |
| 感謝を添える | 「これまでのご厚情に感謝いたします」と加える |
| フォローを加える | 「今後も変わらぬお付き合いを」と結ぶ |
相手によって分けたほうがよいケース
一方で、相手の性格や価値観によっては、喪中と年賀状じまいを同時に伝えることに違和感を覚える方もいます。
特にご年配の方や目上の方は「礼儀を欠いた」と感じる可能性があるため注意が必要です。
その場合は、まずは喪中はがきで「年始の挨拶を控える」旨だけを伝え、翌年以降の年賀状や寒中見舞いで改めて年賀状じまいを知らせる方法も適しています。
まとめると、喪中と年賀状じまいを同時に伝えるかどうかは「相手との関係性」で判断するのが最善です。
| 相手 | おすすめの対応 |
|---|---|
| 親しい友人・同世代 | 同時に伝えて問題なし |
| ご年配・目上 | 喪中のみ伝え、年賀状じまいは別の機会に |
| ビジネス関係 | ケースバイケースだが、フォーマルな文面で慎重に |
喪中と年賀状じまいを同時に伝える文例集
実際に喪中と年賀状じまいを同時に伝える場合、どのように書けばよいか迷いますよね。
ここでは、シンプルな文例からビジネス向けまで、さまざまなケースに応じた具体的な例文をご紹介します。
基本形の例文(最もシンプルな形)
まずは汎用的に使えるシンプルな例文です。
喪中の報告を主にし、最後に年賀状じまいを一言添えるのが基本です。
▼文例
「本年〇月に〇〇(続柄・名前)が永眠いたしました。
ここに本年中賜りましたご厚情に心より御礼申し上げます。
誠に勝手ながら来年より年賀状によるご挨拶を控えさせていただきますが、
今後とも変わらぬご交誼をお願い申し上げます。」
| 特徴 | ポイント |
|---|---|
| 形式的で汎用性が高い | 幅広い相手に使える |
| 年賀状じまい部分は一文 | 喪中が主であることを崩さない |
親しい友人・親族への例文(気持ちを込める場合)
親しい相手には、心情やこれまでの感謝を少し多めに添えると温かみが伝わります。
▼文例
「本年〇月に〇〇(続柄・名前)が永眠いたしました。
長年にわたり年賀状でご挨拶をいただきましたこと、心より感謝申し上げます。
つきましては、これを機に年賀状によるご挨拶を終了させていただきたく存じますが、
これからも変わらぬお付き合いをお願い申し上げます。」
ビジネス関係への例文(フォーマルに伝える場合)
仕事関係や取引先には、礼儀を重んじたフォーマルな表現が必要です。
過度に感情的にならず、簡潔かつ丁寧にまとめましょう。
▼文例
「本年〇月に近親者が永眠いたしましたため、年始のご挨拶を控えさせていただきます。
あわせまして、勝手ながら本年をもちまして年賀状によるご挨拶も終了させていただきます。
今後とも変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。」
高齢者・ご年配への例文(配慮を強調する場合)
ご年配の方は「年賀状じまい」を寂しく感じることもあるため、フォローの言葉が重要です。
感謝と今後の関係性を重ねて伝えると安心感を与えられます。
▼文例
「本年〇月に〇〇(続柄・名前)が永眠いたしました。
これにより新年のご挨拶を控えさせていただきます。
長年にわたり年賀状でお付き合いいただき、心より感謝申し上げます。
勝手ながら今後は年賀状でのご挨拶を終了いたしますが、
これまで以上にご縁を大切にしてまいりたいと存じます。」
| 相手 | 例文の特徴 |
|---|---|
| 友人・親族 | 感謝や思い出を添える |
| ビジネス関係 | 簡潔・礼儀正しい表現 |
| ご年配 | フォローの言葉を必ず入れる |
寒中見舞いやその他で伝える場合の文例集
喪中はがきで年賀状じまいを同時に伝えることに迷いがある場合は、寒中見舞いやその他の手段を使うのも一つの方法です。
ここでは、寒中見舞い・メールやSNS・直接伝える場合の文例をまとめました。
寒中見舞いで喪中と年賀状じまいを同時に伝える例文
寒中見舞いは、松の内が明けた1月8日〜2月上旬に出す挨拶状です。
喪中で年賀状を控えたあと、年賀状じまいも合わせて伝えるのに適しています。
▼文例
「寒中お見舞い申し上げます。
旧年中は大変お世話になりました。
このたびは喪中につき新年のご挨拶を失礼いたしました。
あわせて誠に勝手ながら、今後は年賀状でのご挨拶を控えさせていただきたく存じます。
今後も変わらぬご厚誼をお願い申し上げます。」
| ポイント | 理由 |
|---|---|
| 新年の挨拶を避ける | 喪中に配慮するため |
| 控えめな表現 | 年賀状じまいを柔らかく伝えるため |
メールやSNSで伝えるカジュアルな例文
親しい友人や同世代には、メールやSNSでカジュアルに伝えるのも自然です。
ただし、一斉送信ではなく個別に送る方が、誠意が伝わります。
▼文例
「昨年は大変お世話になりました。
ご存じのとおり、喪中につき新年のご挨拶は控えさせていただきました。
あわせて、今後は年賀状でのご挨拶を終了させていただきたく思います。
これからはメールやSNSでご連絡できれば幸いです。
これからも変わらぬお付き合いをよろしくお願いします。」
直接会ったときに伝える言い回し例
顔を合わせる機会がある相手なら、直接伝えるのが最も誤解を防げます。
表情や声のトーンで丁寧さを示せるため、冷たく受け止められることが少なくなります。
▼言い回し例
「今年は喪中につき新年のご挨拶を控えました。
この機会に年賀状も控えさせていただこうと思っております。
これからは別の形でご縁を続けさせていただければと思います。」
| 方法 | メリット |
|---|---|
| 寒中見舞い | フォーマルかつ穏やかに伝えられる |
| メール・SNS | 気軽でスピーディに伝えられる |
| 直接会って | 誤解なく丁寧に伝えられる |
伝えるタイミングと方法の選び方
喪中と年賀状じまいを同時に伝える場合、いつ・どの方法で知らせるかによって、相手の受け止め方が大きく変わります。
ここでは「喪中はがき」「寒中見舞い」「その他の方法」それぞれの適切なタイミングを解説します。
喪中はがきを使うときのポイント
喪中はがきは、11月中旬から12月初旬に相手へ届くように送るのが基本です。
喪中が主で、年賀状じまいは一言添える程度にすると失礼になりません。
12月中旬以降の不幸は間に合わないこともあるため、その場合は寒中見舞いへ切り替えましょう。
| 送付時期 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 11月中旬〜12月初旬 | 確実に相手に届く | 年賀状じまい部分は控えめに |
| 12月中旬以降 | 無理に出さず寒中見舞いで対応 | 遅れると相手が年賀状を準備してしまう可能性 |
寒中見舞いに切り替える場合
喪中はがきを出しそびれた場合や、伝え方に迷った場合は寒中見舞いがおすすめです。
寒中見舞いは松の内明け(1月8日以降)から2月上旬までに送るのがマナーです。
寒中見舞いは新年のご挨拶ではないため、年賀状じまいを伝える場としても自然です。
迷ったときの判断基準
喪中と年賀状じまいを同時に伝えるかどうか迷ったときは、以下の基準を参考にしてください。
- 親しい友人・同世代:同時に伝えても違和感なし
- ご年配・目上の方:喪中のみ先に伝え、年賀状じまいは寒中見舞いや翌年に
- ビジネス関係:相手との関係性を見極めて判断
迷った場合は、「まず喪中」「あとで年賀状じまい」と段階を踏むと安心です。
相手に誠意が伝わるかどうかを基準に選ぶのが最も大切です。
2025年最新の年賀状じまい事情
近年、年賀状をやめる「年賀状じまい」が急速に広がっています。
ここでは2025年の最新事情を整理し、背景や新しい選択肢について解説します。
年賀状じまいが増加する背景(デジタル化・料金値上げ)
2025年用の年賀はがき発行枚数は、前年比で25.7%減と過去最大の減少率となりました。
はがき料金が63円から85円に値上がりしたことに加え、LINEやメールなどデジタルでのやり取りが一般化したことも大きな要因です。
「コスト負担」と「デジタル移行」が、年賀状じまいを後押ししていると言えるでしょう。
| 要因 | 内容 |
|---|---|
| 料金値上げ | 2024年に85円へ引き上げ |
| デジタル普及 | SNSやメールでの新年挨拶が当たり前に |
| 社会の簡素化志向 | 形式よりも実質的なつながりを重視 |
部分的な年賀状じまいという選択肢
一気にすべてをやめることに抵抗がある方は、段階的に減らす方法もあります。
たとえば「親しい人だけ続ける」「届いた年賀状にだけ返事を出す」といった形です。
この柔軟な対応が、今後の主流になりつつあります。
▼部分的な年賀状じまいの具体例
- 親戚や親しい友人だけに出す
- 会社関係は続けるが、プライベートはやめる
- 届いた人にだけ返事を返す
「喪中」と重なった場合も、この考え方を取り入れることで、相手に違和感を与えずに移行できます。
| やめ方 | メリット |
|---|---|
| 一気にやめる | 手間・コストが一度に解消 |
| 部分的にやめる | 相手に寂しさを与えにくい |
喪中・年賀状じまい同時連絡のQ&A
最後に、読者からよく寄せられる疑問をQ&A形式で整理しました。
実際の対応に迷ったときの参考にしてください。
よくある疑問とその答え(複数の具体例付き)
Q1:喪中を伝える相手全員に、年賀状じまいも同時に知らせるべき?
A1:必ずしも全員に同時に伝える必要はありません。
親しい友人やこれからも関係を続けたい人には同時に伝えて構いませんが、ご年配や目上の方には別のタイミングで伝える方が無難です。
Q2:喪中と年賀状じまいを同時に伝えると、内容が重くなりすぎませんか?
A2:文章の主軸を「喪中」に置き、年賀状じまいは一言添える程度にすると、重さを避けられます。
▼例文
「本年〇月に近親者が永眠いたしましたため、年始のご挨拶を控えさせていただきます。
あわせまして誠に勝手ながら、年賀状によるご挨拶も本年をもちまして控えさせていただきます。」
Q3:喪中はがきで年賀状じまいを伝えたのに、相手から年賀状が届いてしまったら?
A3:その場合は「寒中見舞い」でフォローするのが最適です。
▼例文
「寒中お見舞い申し上げます。
先般は年賀状をいただき誠にありがとうございました。
喪中につき新年のご挨拶を控えておりましたが、あわせて年賀状によるご挨拶を終了させていただいております。
今後とも変わらぬお付き合いをお願い申し上げます。」
Q4:ビジネス関係にはどう対応すべきですか?
A4:ビジネス相手には礼儀を重視しましょう。
▼例文
「このたび近親者が永眠いたしましたため、年始のご挨拶を控えさせていただきます。
また誠に勝手ながら、今後は年賀状によるご挨拶も控えさせていただく所存です。
引き続き変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。」
| 疑問 | 対応方法 |
|---|---|
| 全員に同時に伝えるべき? | 相手により使い分け |
| 内容が重すぎないか? | 喪中を主にし、年賀状じまいは一文だけ |
| 年賀状が届いてしまった場合 | 寒中見舞いでフォロー |
| ビジネス相手への対応 | 礼儀正しく、簡潔に伝える |
まとめ 喪中と年賀状じまいは「丁寧さ」と「思いやり」で
喪中と年賀状じまいを同時に伝えることは、決して失礼ではありません。
むしろ自然な流れとして受け止めてもらえる場合も多いですが、相手によっては驚かせてしまう可能性もあります。
最も大切なのは「相手への思いやり」と「言葉の丁寧さ」です。
今回ご紹介した文例を参考に、自分の立場や相手との関係性に合わせて使い分けましょう。
ご年配や目上の方には配慮を欠かさず、友人や同世代にはカジュアルに伝えるなど、相手に合わせる工夫が大切です。
| 伝え方 | ポイント |
|---|---|
| 喪中はがきで同時に伝える | 喪中が主、年賀状じまいは一文 |
| 寒中見舞いで伝える | フォーマルに柔らかく伝えられる |
| メールやSNSで伝える | 親しい相手にカジュアルに |
| 直接伝える | 誤解を防ぎ、誠意を伝えやすい |
喪中も年賀状じまいも、単なる形式ではなく「これまでありがとう」「これからもよろしく」という気持ちを届ける場面です。
あなたらしい言葉で、大切な人とのつながりをこれからも続けていきましょう。