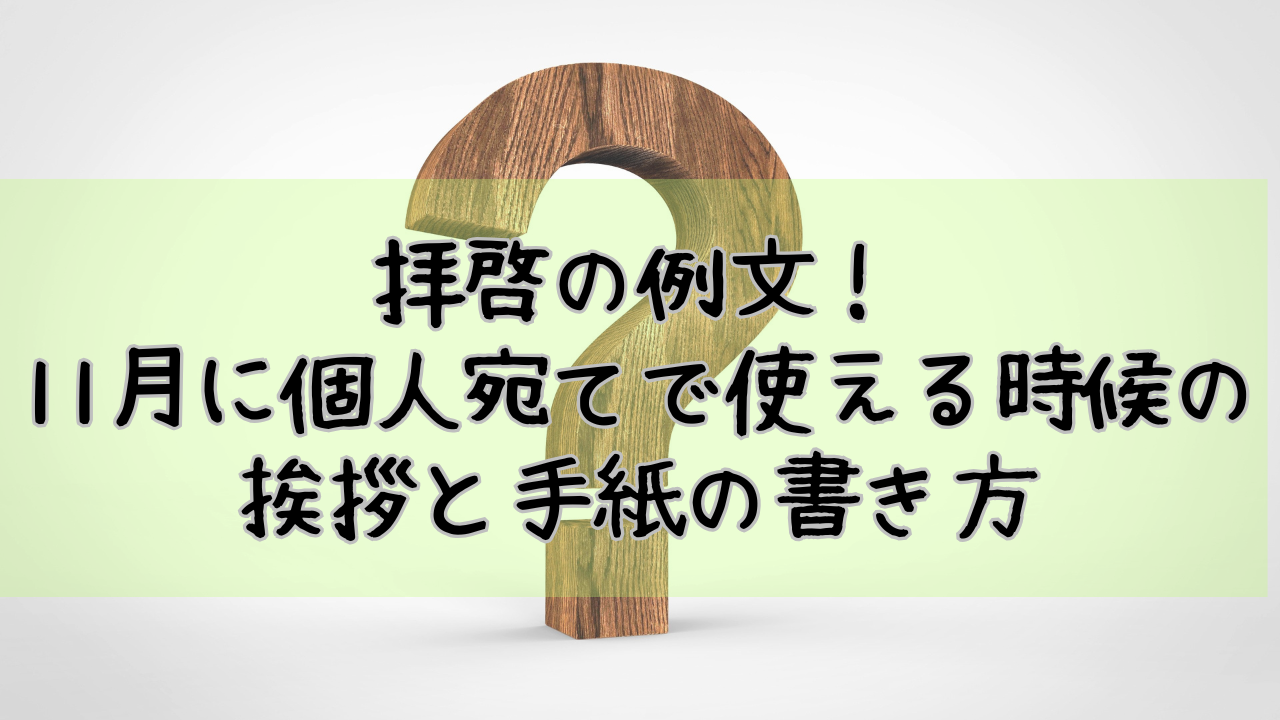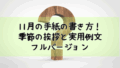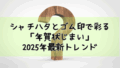11月は秋から冬への移ろいを感じる季節で、紅葉や小春日和、初雪など多彩な情景が広がります。
そんな時期に個人宛ての手紙を書くなら、「拝啓」から始まる時候の挨拶や結びの言葉を工夫するだけで、文章がぐっと温かみを増します。
本記事では、11月の上旬・中旬・下旬ごとに使える「拝啓」の例文を豊富に紹介し、実際に使えるフルバージョンの手紙サンプルも掲載しました。
また、本文を自然に仕上げるための近況や感謝の伝え方、季節の話題を盛り込むコツも詳しく解説しています。
11月らしい季節感を大切にしつつ、相手を思いやる手紙を書きたい方に最適な完全ガイドです。
形式を守りながらも自分らしい言葉を添えて、心に残る一通を綴ってみませんか。
11月に個人宛ての手紙で使う「拝啓」の基本ルール
11月に個人宛てで手紙を書くとき、最初に迷うのが「拝啓」から始まる書き出しのルールです。
ここでは、基本の流れや「頭語と結語」の組み合わせ、さらに個人宛てならではの工夫について解説します。
手紙の基本構成と頭語・結語の関係
手紙は、一般的に以下の流れで構成されます。
| 要素 | 役割 | 例 |
|---|---|---|
| 頭語 | 手紙の冒頭に置く決まり文句 | 拝啓、前略 |
| 時候の挨拶 | 季節を感じさせる挨拶 | 晩秋の候、紅葉の折 |
| 安否の確認 | 相手の健康や近況を気づかう | お元気でいらっしゃいますか |
| 本文 | 伝えたい内容 | 近況報告、感謝の気持ち |
| 結びの挨拶 | 相手の健康や幸福を祈る | ご自愛ください |
| 結語 | 頭語と対応する締め言葉 | 敬具、草々 |
「拝啓」と書き始めたら、必ず「敬具」で締めるのが基本です。
これは、フォーマルさを保つための決まりごとであり、プライベートな手紙でも意識すると美しい印象になります。
親しい相手だからこそ意識すべきポイント
友人や家族などの個人宛ての手紙では、堅苦しすぎる必要はありません。
例えば「拝啓」を省略して「こんにちは」や「ご無沙汰しています」から始めても良いですが、改まった雰囲気を出したいときは「拝啓」から入るのがおすすめです。
その場合、相手の生活や体調に寄り添った表現を入れることで、文章が一気に温かみを帯びます。
たとえば「朝晩冷え込む季節となりましたが、風邪など召されていませんか」という一文を加えるだけで、気遣いのある手紙になります。
11月に個人宛ての手紙で使う「拝啓」の基本ルール
11月に個人宛てで手紙を書くとき、最初に迷うのが「拝啓」から始まる書き出しのルールです。
ここでは、基本の流れや「頭語と結語」の組み合わせ、さらに個人宛てならではの工夫について解説します。
手紙の基本構成と頭語・結語の関係
手紙は、一般的に以下の流れで構成されます。
| 要素 | 役割 | 例 |
|---|---|---|
| 頭語 | 手紙の冒頭に置く決まり文句 | 拝啓、前略 |
| 時候の挨拶 | 季節を感じさせる挨拶 | 晩秋の候、紅葉の折 |
| 安否の確認 | 相手の健康や近況を気づかう | お元気でいらっしゃいますか |
| 本文 | 伝えたい内容 | 近況報告、感謝の気持ち |
| 結びの挨拶 | 相手の健康や幸福を祈る | ご自愛ください |
| 結語 | 頭語と対応する締め言葉 | 敬具、草々 |
「拝啓」と書き始めたら、必ず「敬具」で締めるのが基本です。
これは、フォーマルさを保つための決まりごとであり、プライベートな手紙でも意識すると美しい印象になります。
親しい相手だからこそ意識すべきポイント
友人や家族などの個人宛ての手紙では、堅苦しすぎる必要はありません。
例えば「拝啓」を省略して「こんにちは」や「ご無沙汰しています」から始めても良いですが、改まった雰囲気を出したいときは「拝啓」から入るのがおすすめです。
その場合、相手の生活や体調に寄り添った表現を入れることで、文章が一気に温かみを帯びます。
たとえば「朝晩冷え込む季節となりましたが、風邪など召されていませんか」という一文を加えるだけで、気遣いのある手紙になります。
個人宛てに使える「拝啓」例文集【11月上旬・中旬・下旬】
実際に手紙を書くときにすぐ使える例文が欲しいですよね。
ここでは、11月上旬・中旬・下旬に分けて、親しい人に向けた「拝啓」の書き出し例を紹介します。
11月上旬に使える拝啓例文
秋の深まりや菊の花が見頃を迎える時期です。
柔らかな季節の雰囲気を表現した例文が向いています。
| 例文 | ポイント |
|---|---|
| 拝啓 菊花の季節となりましたが、お変わりありませんか。 | 秋の花を取り入れると華やかさが増す |
| 拝啓 街路樹の葉が赤や黄に色づき、秋も深まってまいりました。お元気でいらっしゃいますか。 | 紅葉を具体的に描くと臨場感が出る |
| 拝啓 朝晩の冷え込みが一段と増しましたが、お体にお変わりはございませんでしょうか。 | 健康を気遣う一言を加えると温かみが出る |
11月中旬に使える拝啓例文
立冬を迎え、冬の入口を意識した言葉が合います。
また、小春日和のようなやわらかな気候を表す表現もおすすめです。
| 例文 | ポイント |
|---|---|
| 拝啓 立冬を迎え、冬の足音が近づいてまいりました。いかがお過ごしですか。 | 二十四節気を取り入れると格調が上がる |
| 拝啓 暦のうえでは冬となりましたが、穏やかな小春日和が続いております。お元気でいらっしゃいますか。 | 「小春日和」は11月ならではの風情 |
| 拝啓 菊の香りが街に漂う季節となりました。ご健勝にてお過ごしのことと存じます。 | 香りの表現で情景をより豊かにできる |
11月下旬に使える拝啓例文
冬が近づき、年末を意識する頃です。
寒さや季節の区切りを表現すると自然な文章になります。
| 例文 | ポイント |
|---|---|
| 拝啓 晩秋の候、夜の冷え込みが厳しくなってまいりました。お変わりございませんか。 | 晩秋という表現で季節感を強調 |
| 拝啓 初雪のたよりが聞こえる季節となりました。お元気でお過ごしでしょうか。 | 「初雪」という言葉で冬らしさを出す |
| 拝啓 今年もいよいよ残り少なくなってまいりましたが、お変わりなくお過ごしでしょうか。 | 年末を意識した一言は11月後半にぴったり |
「拝啓」の後に季節感と気遣いを添えると、それだけで手紙が温かみのあるものになるのです。
手紙本文を自然に仕上げるためのコツ
「拝啓」で始めた手紙を、自然で温かみのあるものにするには工夫が必要です。
ここでは、近況や感謝の伝え方、そして11月らしい行事や話題を取り入れる方法を紹介します。
近況や感謝の言葉を盛り込む方法
時候の挨拶の後には、相手や自分の近況を添えると文章に厚みが出ます。
さらに、過去のやり取りへの感謝を入れると、丁寧で心のこもった手紙になります。
| 例文 | ポイント |
|---|---|
| 先日は温かなお心遣いをいただき、誠にありがとうございました。 | 具体的に「先日」とすることで、やり取りを思い起こさせる |
| お元気でお過ごしのご様子、何よりと存じます。私どもも変わりなく暮らしております。 | 相手と自分の近況を対比させて安心感を与える |
| ご無沙汰いたしましたが、変わらずご健勝とのこと、心より嬉しく思います。 | 久しぶりの手紙に使いやすいフレーズ |
「相手→自分→感謝」の流れを意識すると、読みやすく自然な文になるのがコツです。
季節行事や話題を添える工夫
11月は、七五三や紅葉、鍋料理など季節の話題が豊富です。
身近な出来事を取り入れると、より親しみを感じてもらえます。
| 例文 | 話題 |
|---|---|
| 週末は家族で紅葉狩りに出かけてまいりました。鮮やかな色合いに心が和みました。 | 紅葉 |
| こたつを出し、鍋料理が食卓をにぎわせる季節となりました。 | 冬支度・食文化 |
| 近所の神社では七五三のお祝いで華やいでおり、季節の移ろいを感じます。 | 七五三 |
形式的すぎると味気なくなるので、日常の一コマを添えるのが効果的です。
たとえば「おでんが恋しい季節ですね」と一言入れるだけでも、手紙全体が和やかになります。
11月にふさわしい結びの挨拶と例文
手紙の最後をどう締めくくるかで、相手に残る印象は大きく変わります。
11月は寒さが増し、年末も近づくため、健康や幸せを願う言葉が特に喜ばれます。
健康や幸せを願う言葉
11月の結びには、気温の低下を意識した気遣いが欠かせません。
以下のような表現を添えると、相手に安心感を与えられます。
| 例文 | ポイント |
|---|---|
| 日に日に寒さが募りますので、どうぞお健やかにお過ごしください。 | 気候を踏まえて健康を願う |
| お風邪など召されませんよう、ご自愛ください。 | 体調管理を思いやる表現 |
| 寒さが厳しくなります折、温かくしてお過ごしください。 | 生活面への気遣いを含める |
体調を気遣う結び文は、個人宛ての手紙で最も使いやすいパターンです。
年末を意識した結び表現
11月下旬は、自然と年末を思わせる時期です。
未来を見据えた言葉を入れると、余韻のある手紙になります。
| 例文 | ポイント |
|---|---|
| 今年も残りわずかとなりましたが、どうぞ良いお年をお迎えください。 | 年末にふさわしい挨拶 |
| 来年も素晴らしい一年となりますよう、お祈り申し上げます。 | 前向きな気持ちを共有できる |
| 年末に向けご多忙かと存じますが、どうかお体を大切になさってください。 | 忙しさと健康の両方を気遣う |
11月後半は「健康」と「年末」の二つを意識した結びが自然です。
例えば「新しい年に向け、どうぞお元気でお過ごしください」といった言葉は、季節に合った温かな締めくくりになります。
【完全サンプル】11月に使える個人宛ての手紙全文例
ここまで紹介したポイントを踏まえて、実際に使えるフルバージョンの例文をまとめました。
11月の上旬・中旬・下旬に分けて紹介しますので、そのまま使っても、少しアレンジしても大丈夫です。
11月上旬の手紙例文
| 拝啓 菊花の季節となりましたが、お変わりありませんか。
こちらでは朝晩がぐっと冷え込むようになり、秋の深まりを感じております。 先日は温かなお心遣いをいただき、誠にありがとうございました。 家族そろって楽しい時間を過ごすことができ、大変感謝しております。 紅葉も色づきはじめ、散歩が楽しみな毎日です。 季節の変わり目ですので、どうぞお体を大切になさってください。 敬具 |
11月中旬の手紙例文
| 拝啓 暦のうえでは冬となりましたが、穏やかな小春日和が続いております。
皆さまにはお元気でお過ごしのことと存じます。 先日のお便り、楽しく拝読いたしました。私どもも変わりなく暮らしております。 近所の神社では七五三のお祝いが行われ、華やかな雰囲気に包まれています。 寒さが増すこれからの季節、どうぞお健やかにお過ごしください。 敬具 |
11月下旬の手紙例文
| 拝啓 初雪のたよりが聞こえる季節となりました。
お変わりなくお過ごしでしょうか。 いよいよ年末が近づき、何かと慌ただしい頃となりました。 我が家では冬支度も整い、鍋料理やこたつが欠かせない毎日です。 新しい年を健やかに迎えられますよう、心よりお祈り申し上げます。 敬具 |
フルバージョンの手紙は「季節感+近況+結び」の3要素で構成するとバランスが良いです。
そのまま使っても失礼にあたらず、応用もしやすいので、11月の手紙作成にとても便利です。
11月らしい表現を豊かにするための工夫
せっかくの手紙も、ありきたりな表現ばかりだと印象が薄くなってしまいます。
ここでは、11月らしさを引き立てる言葉や、やわらかな言い回しを紹介します。
季節感を表す言い回し一覧
紅葉や冷え込みなど、11月ならではの風景を取り入れると雰囲気が深まります。
| 表現 | ニュアンス |
|---|---|
| 落ち葉が舞い散る景色 | 晩秋らしさをダイレクトに伝える |
| 朝夕の冷え込み | 季節の変わり目を強調できる |
| こたつの温もり | 生活感を出し、親近感を与える |
| 初霜の知らせ | 冬の訪れを予感させる |
| 紅葉の見ごろ | 彩りある季節感を演出できる |
景色や体感を入れると、言葉が一気に立体的になるのが魅力です。
柔らかい語感や身近な話題の活用
親しい人への手紙なら、少し砕けた表現や日常の話題を入れても構いません。
堅すぎない言葉を選ぶことで、距離感がぐっと縮まります。
| 表現 | 使い方の例 |
|---|---|
| 温泉が恋しい季節となりました | 旅行や癒やしの話題につなげられる |
| 夜長のつれづれにふとあなたを思い出しました | 感傷的で温かな雰囲気を演出 |
| おこたが恋しい季節となりました | 家庭的で親近感ある印象を与える |
| 鍋料理が食卓をにぎわせています | 季節感と生活感を同時に表現できる |
たとえば「温泉が恋しくなる季節ですね」と書けば、読み手も自然とその情景を想像しやすくなります。
11月の手紙は、形式美と親しみやすさの両立がポイントです。
まとめ|11月の「拝啓」例文を個人宛てに使うときのポイント
ここまで11月にふさわしい「拝啓」の使い方や例文を紹介してきました。
最後に、手紙を仕上げる際に押さえておきたいポイントを整理します。
| チェックポイント | 内容 |
|---|---|
| 時候の挨拶 | 上旬・中旬・下旬で変化をつける(紅葉、小春日和、初雪など) |
| 本文 | 近況報告や感謝を交え、身近な話題を入れると自然 |
| 結び | 寒さや年末を意識し、相手の健康や来年への思いを添える |
| 結語 | 「拝啓」で始めたら「敬具」で締めるのが基本 |
11月の手紙は「秋から冬への移ろい」を意識することが最大のポイントです。
紅葉・七五三・鍋料理・初雪といった話題を入れると、相手の心に残る温かな手紙になります。
形式を守りつつも、あなたらしい言葉を添えることで、唯一無二の一通になるでしょう。